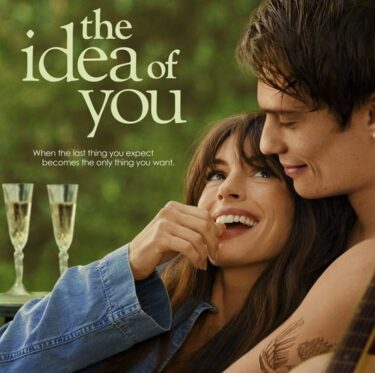2024年3月22日公開の映画『四月になれば彼女は』を初日に鑑賞!
川村元気さんの人気小説が、佐藤健、長澤まさみ、森七菜で実写化されました。
映画『四月になれば彼女は』ネタバレあらすじ解説
©︎公式サイト
精神科医の・藤代俊(佐藤健)の婚約者・坂本弥生(長澤まさみ)が、4月1日の誕生日に失踪する。
藤代は弥生を探すが、なぜか必死になれない。バーテンダーのタスク(仲野太賀)や、弥生の妹・純(河合優実)にも「おまえに問題がある」と指摘された。
弥生は動物園に勤める獣医で、藤代の元患者だった。結婚を約束する相手がいたが本気になれず、不眠症だったのだ。
弥生は藤代と恋に落ちたことで、不眠症が治った。
藤代には10年前の大学生の時に大好きだった春(森七菜)との忘れられない思い出があった。大学の先輩後輩の関係で、同じ写真部だった。
恋に落ちた藤代と春はボリビアのウユニ湖や、プラハの時計台、アイスランドのブラックサンドビーチをめぐって写真を取る海外旅行の計画を立てた。
しかし春の父親(竹野内豊)に反対されてしまう。
藤代は2人で海外旅行に行こうと言う。春は空港まで来たものの、引き返すことを決意した。その出来事をキッカケに2人の関係は終わったのだ。
以前、春から手紙が届いた。藤代と行くはずだったウユニ湖、プラハの時計台、アイスランドのブラックサンドビーチを1人で旅したこと、そして写真が同封されていた。弥生もその手紙を見る。
弥生からの手紙が届く。同棲して時間が経つにつれ、お互いの気持ちが冷めていったことがつづられていた。
藤代に大学の頃の親友・ペンタックスから電話が入る。春が死んだらしい。
春は不治の病を患っており、海辺のホスピスで最後の時を迎えたようだ。
藤代はそのホスピスへ行く。担当者から春のカメラとフィルムを渡された。
藤代はフィルムを現像してみた。すると、失踪したはずの弥生が写っている。弥生はホスピスで働いていたのだ。
弥生は以前に春からきた手紙で動揺し、藤代への気持ちを失っていない春に会うためにホスピスに勤務していたのだ。
藤代はホスピスへ向かう。弥生が砂浜に立っていた。藤代に気づいた弥生は逃げる。藤代は弥生を追いかけて抱きしめた。朝陽とともに、愛が再び輝き出す。
映画『四月になれば彼女は』感想・評価(ネタバレ)
良かった点

藤井道人監督の『ヤクザと家族 The Family』『余命10年』や川村元気さんの『百花』を担当した今村圭佑さんが撮影だったこともあってか、映像が壮大かつ美しかったです。
黒い砂浜と白い波の対比が美しすぎます。
全体的に森七菜さんが海外で写真撮影をしているシーンは眼福でしたね。
佐藤健さんと森七菜さんの、大学キャンパスでのみずみずしい恋愛模様も、ベタですがステキでした。
森七菜さんの初々しさや雰囲気がとにかく物語にハマりまくっています。抜群のキャスティングでした。
「初恋の喪失が、現在の喪失を埋める」という、喪失で喪失を埋める抽象的なコンセプトにもグッときました。
微妙だったところ
まずプロデューサーの川村元気さんは原作小説について、「愛がないことを描いた物語。愛の不在の物語」と語っており、愛の不可能性がテーマのひとつだと語っています。
ただ少なくとも映画版ではそこまで深いテーマが感じられなかったというか、どちらかといえば「愛の不在が単なる過程でしかない普通の恋愛映画」にかたむいていた気がします。どっちつかずです。
また個人的に1番ひっかかったのが、藤代と弥生が同居しながら別々の部屋で寝るほど冷めた関係だったこと。
私自身のつたない恋愛経験からしても、完全に愛が死んでいる末期状態に見えました。リアルさが求められる実写だと、その状態から愛が復活することに無理やり感があります。
「愛を失わない方法は、愛を1度死なせて復活させること」。そんな抽象的なメッセージがあるのかもしれません。
藤代と弥生の愛が1度死んだことと、春が死んだことが重なってみえる意図もあったのかもしれません。
でもリアルに考えると、藤代と弥生のような倦怠期とも違う冷めた感じは、復活させずに次に進んだ方が幸せな気がします。
子供もいない状態ですでに「結婚15年目の仮面夫婦」みたい。さすがに設定に行き過ぎ感・違和感を感じました。
あとは、佐藤健さんと長澤まさみさんと比べて、森七菜さんだけ若すぎるのがひっかかりました。
話の流れ的には、藤代と弥生は30代前半、春は20代後半。年齢は少ししか変わらないはずです。
ただ実際は長澤まさみさんが2024年時点で36歳、森七菜さんが22歳と14歳差。後半で2人が並んだときに違和感がありました。
また本作には、初恋と現在の恋の対比、自分の問題は自分では解決できない、愛の喪失と再生といった複数のテーマがありましたが、うまくブレンドされていなかった気がします。
テーマ同士が収斂(しゅうれん)されていくのではなく、個々のテーマが独立している印象でした。
弥生や春は親子関係に問題があったこともわかっています。こちらも小さなテーマです。さらに、邦画お決まりの不治の病。
いろんな要素があることが問題というより、「こういう要素を入れ込んでみよう!」という感じが伝わってくるというか、頭でっかちな感じが良くないと思いました。
最近の川村元気さんの作品に共通しているのが言葉で表現できない概念的なものを映像で伝えようとして、100%うまくいっているとは言えないこと。
言語化がむずかしいものを感覚で何とかするのではなく、言葉で表現しようとしてしまっているような気がします。
この矛盾が「愛を失わないためには手に入れなければいい」という、哲学をこじらせたようなセリフにもにじみ出ています。
悪く言えば全体的に「計算できないものを計算して作ろうとしている作為的な感じが漂っている」ともいえるでしょう(ある面でクリエイターの一生の課題なのかもしれませんね)。
映画『四月になれば彼女は』考察(ネタバレ)
「手に入れなかった者」と「手に入れた者」
本作のメインコンセプトは「手に入れなかった者」と「手に入れた者」の対比でしょう。
藤代との愛を手に入れなかった者=春であり、手に入れた者=弥生です。
愛を手に入れた弥生ですが、「愛を失わないためには、手に入れなければいい」と語るなど、幸せに対して抵抗感を持っていました。
そして藤代との関係は冷え切っていきます。
弥生は春と会い、彼女が藤代に当てた最後の手紙を読んだことで、「愛を失わないためには、手に入れなければいい」という自分の答えが間違っていると気づいたのでしょう。
初恋メタファーとしての春
春(森七菜)にはストーリー上の明確な役割があります。初恋のメタファーです。
初恋は、愛に変化できなかったものの象徴です。春のように初恋にすがり続けるなら、愛を失わずにすみます。
『四月になれば彼女は』には、死んだ初恋=春が、藤代の現在の恋愛のエネルギーとなるメッセージが込められていました。
4月の意味、幸せへと進めない存在・弥生
四月一日生まれなのに、三月を表す弥生という名前…。
タイトルの『四月になれば彼女は』からわかる通り、四月は幸せの象徴なのでしょう。
弥生は三月から四月に進めない=幸せになれない可哀想な存在なのです。
本来は4月生まれなので、幸せになる権利を持っています。
ただ、学校が下の学年と同じになる社会の勝手な決まりが象徴するように、幸せになれないという固定観念にとらわれているのです。
ラストで春の手紙を読み、さらに藤代に抱きしめられ、弥生はやっと四月に進むことができたのでしょう。