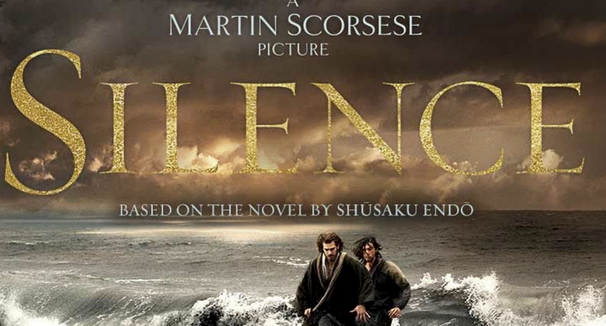マーティン・スコセッシ監督が、遠藤周作の同名小説を映画化した『沈黙 -サイレンス-』。
個人的な感想を言わせてもらえば、スコセッシ作品のなかでも最高の部類に入るものだった。
この映画にかけた費用は約56億円。しかし、興行収入は世界で25億円ほど・・・めっちゃ赤字である。
なるほど、スコセッシがMCUに愚痴を言いたくなるのも当然だ。しかし、受けない理由はめちゃくちゃシンプル!
この記事では『沈黙 -サイレンス-』が予想以上にヒットしなかった理由や、作品が本当に伝えたかったこと、スコセッシの侘び寂び、その他ロケ地などについての考察をしていく!
※ネタバレ有りなので、観てない人は注意してね!
映画『沈黙 -サイレンス-』心理描写の感想・評価(ネタバレ)
映画『沈黙 -サイレンス-』は心理描写がすごい映画だと思う。
なぜ、これほどまでに登場人物の心情や人の心理について考えさせられるのだろうか?
それを紐解くために、まず『沈黙 -サイレンス-』のあらすじを簡単に説明する。
ポルトガル人であるセバスチャン神父 (アンドリュー・ガーフィールド)が、行方不明になっているフェレイラ神父(リーアム・ニーソン)を探しに長崎に着くが、キリシタンを弾圧している井上筑後守(イッセー尾形)に捕らえられ、最後には“踏み絵”を踏んでキリスト教を捨て暮らしていくという物語。
しかし、状況は一筋縄ではいかない。
セバスチャン個人の葛藤

あらすじをふまえ、わかりやすいセバスチャン神父個人の葛藤からみていこう。
- “踏み絵”を踏まないと拷問される
- セバスチャンが信仰を捨てないと、身代わりに日本のキリシタンが死ぬ
- “神”は沈黙しているだけ
この3点から、セバスチャンがキリスト教徒であり続ける大きな葛藤が生まれる。
彼がキリスト教を捨られないせいで、大勢の人間が死んでいく。
セバスチャンが抱える最大の疑問は、この状況でイエス・キリストならどうするか?または彼はユダを許すか?ということ。
イエス・キリストなら、ユダ(棄教という裏切り)を許すかもしれないし、キリスト自身がこの状況なら宗教を捨ててみんなの命を救うかもしれない。
だから、信仰を捨てたセバスチャンを単純に責めることはできないし、そもそも信仰を失うとはどういうことか?という非常に深く、答えのない問いが生まれる。
これだけでもかなり複雑だが、個人を超えたもっと大きな枠組みについて考えさせられる。
これが観客による登場人物の心理の捉え方を、より俯瞰的(ふかんてき)で複雑なものにしている。
視聴者が心情を俯瞰的に捉える理由
- 井上は神父を殺すのではなく、寝返らせてキリシタンを説得させようとしている。
- キリスト教は仏教と相容れないのかという疑問
- 日本で独自に変容しているキリスト教
地域を統治する井上奉行(イッセー尾形)には、キリシタンに個人的な恨みはないが、仕方なくやっているような心情が見受けれられる。
弾圧についても、神父を寝返らせ、キリシタンを説得させるという、合理的な方法だ。
井上はキリストの教えを理解せずに否定する、バカな悪者ではないのだ。むしろ問いを投げかける存在として描かれている。
この辺の見せ方のバランスがすごい。
つぎに、キリスト教と仏教は相容れないのか?という問題。
セバスチャンはこの問いに対して全く明確な答えを出しておらず、二つともアプローチの違いと考えている井上の方が、正しく見えてしまう場面もある。
そして、キリスト教の土着問題について。
日本に入ったキリスト教は日本のアニミズムの影響を受けて変容している。
そこに、宗教の土着や変容はいけないことなのか?本当に相容れないものなのか?という答えの出ない疑問が、また生まれる。
これをもっと広くとらえると、セバスチャンはキリスト教を捨てたが、教義に多様性を見つけて独自に解釈し、日本の生活にもキリスト教的な心を見い出して、救われていたのかもしれない。
そこにはアニミズムが介在していたのだろうか。テーマが深すぎる。
『沈黙 -サイレンス-』心理描写のまとめ
心理描写についてまとめると、『沈黙 -サイレンス-』では、宗教の意義、疑問、本質など、根本的な部分がテーマとなっており、すぐに答えが出せるものではない。
しかしそれが、視聴者が捉える登場人物の心理描写を複雑に、そしてより味わい深いものにしている。
映画『沈黙 -サイレンス-』ネタバレ考察/スコセッシが理解した日本の感性
スコセッシはずっと前から遠藤周作の小説を映画化したかったようだが、彼が映像で表現した日本の原風景からもその執念が感じられる。
そこにはいわゆる“とんでも日本“”は微塵も存在しない。
それどころか、日本人として学びたくなるような素晴らしい世界観だった。スコセッシは、もしかして侘び寂びを理解している?そうとしか考えられないのだ。
蝉の声や波の音
『沈黙 -サイレンス-』では派手な音楽は一切使われず、オープニングやエンディングで蝉の声や、波の音を黒い画面のバックで流していたのが印象的だった。まるで、最初と最後に、ある答えを提示していたかのようだ。
多くの評論家が、自然音を流すことで沈黙を表していたと言うが、本当にそれだけだろうか。
『沈黙 -サイレンス-』サイレンスでは沈黙の中に神の声を求めるが、聞こえてくるのは、蝉の声(ヒグラシ)や波の音。神の声=蝉の声や波の音と捉えることができるのではないか。
もしかしたらスコセッシは、キリスト教とアニミズムの融合を描いていたのかもしれない。だとしたら、美的感覚が素晴らしすぎる。
相容れないと思われる二つの宗教だが、通底するものがある。
そう考えると、キリスト教を捨てたからと言って神から離れたことにはならないし、日本文化のうちで暮らしても、神は側にいるといえる。
この考え方そのものが“侘び寂び”なのかもしれない。
形式的に「とりあえず踏め」
井上の部下は踏み絵を踏むのを形式的なものだと割り切っており、とりあえず踏めば許すこともあった。これはまさしく“建前”。
本音と建前まで完璧に表現していたことに驚き!
井上の置かれている状況

井上はキリスト教に対して恨みは持っていないが、弾圧はしている。
しかし、セバスチャンに対しての敬意もみえ、全てを丸く治めようとしている節(ふし)が見受けられる。
日本の社会では、上からの無理難題を、根回しをして上手く解決するという美談がよくあるが、スコセッシは、その点も理解しながら映画を撮っているようにしか思えない。
映画『沈黙 -サイレンス-』テーマ考察
結局、沈黙-サイレンス-という映画が伝えたかったことは何なのか?まとめてみた!
みんなの踏み絵体験
沈黙-サイレンス-という映画の大きなポイントは、みんなが“踏み絵”体験できるということだ。
自分の信じているものを捨てなければいけない状況におかれ、どういう心情になるか真剣に考えることには、ものすごい意義がある。
カメラワークも、臨場感を抜群に与えてくれるものとなっており、特にカトリック信者は拷問などからキリストの犠牲や苦悩、ユダの行いについて考えることができる仕掛けになっている。
ある意味踏み絵のテーマパーク映画(笑)カトリック信者のマーティン・スコセッシらしい演出だ。
信じているからこそ対等に描く!
沈黙-サイレンス-では、キリスト教と仏教や日本のアニミズム文化が対等に描かれている。
キリスト教に対して大きな疑問を投げかけているのだが、もう少し踏み込んで考えれば、対等に描くということは、キリスト教に対する信仰の裏返しでもある。
映画の中でキリスト教を疑うような、考え得るどんな疑問をぶつけても、“万能な神”が自分以上の答えを提示してくれる。
スコセッシは映画制作に対して、そのような信仰を持って挑んだのかもしれない。同じくキリスト教徒である遠藤周作が原作に込めた真意は、彼しか受け継ぐことができなかっただろう。
日本への布教を正当化
カトリックイエズス会の日本への布教に関しては常に、「日本古来のアニミズムや仏教を否定して、キリスト教を広めるなんて傲慢ではないか?」という疑問の声があがる。なるほど、確かに傲慢かもしれない。
物事の本質を捉えられるスコセッシなら、当然この点について考えたはずだ。だからこそ、セバスチャン神父の迷いを描き、苦悩し、最後は日本の文化に溶け込むという描き方をした。
さらに深く考えてみると、セバスチャン自身が教義そのものであり、最後は日本に溶け込むということは、キリスト教は沼である日本に吸収されたかに見えて、どこかに何処かに根付いている。無駄ではなかったということを正当化をしていると考えられないだろうか。
もしかすると、現代日本人がクリスマスを受け入れて素直に楽しめているのは、この時代のイエズス会の布教が背景にあるのかもしれない。
ラスト:ずっと聞こえていた神の声
沈黙し続けたときに神の声が聞こえてくる。しかし、みんなが沈黙したときに聞こえてくるのは虫の声や波の音。
もしかして、神の声はずっと聞こえいたのではないか?それが虫の声や波の音である。
通常これは、キリストの教義ではなく、万物に神が宿るというアニミズムの思考だが、スコセッシは一歩進んで、キリスト教とアミニズムに通底するものがないか?もしかすると神の声は自然の音として、ずっと聞こえていたのではないか?ということを表現しているようにおもえてならない。
映画『沈黙 -サイレンス-』赤字の理由解説!つまらない?

僕がめちゃくちゃ感動した『沈黙 -サイレンス-』が赤字になっていたなんて悲しすぎる!だが、心当たりありまくり。理由は以下。
エンタメ要素ゼロ
映画『沈黙 -サイレンス-』の舞台は17世紀。江戸自体初期の長崎の僻地。
画面の大半を占めるのが、小汚い村人と小汚い小屋。あとは自然。リアリティは抜群だ。
しかし、わかりやすいエンタメ要素は一切なし。
スコセッシ監督の『アビエイター』とか『ウルフ・オブ・ウォール・ストリート』などの作風を期待すると、つまらないと感じるかもしれない。
映画に派手さや刺激を求める人に、この『沈黙 -サイレンス-』を観せようものなら、5分で寝てしまうだろう。「自然そのものがエンタメだ」と達観しているような人間に向いている作品だ。
土地の独自の文化と登場人物の葛藤を表現している点で、アリ・アスター監督による北欧のフォークホラー『ミッドサマー』に通底する部分はあるが、『沈黙』の方が格段に渋く、エンタメ要素は薄い。
ボーッと観てるとつまらない
『沈黙 -サイレンス-』においてスコセッシ監督は、キリスト教側が正しく、日本人が酷いという描き方はしていない。
だからこそ、単純に登場人物に感情移入してしまうと、心理描写が上手くつかめない。
視聴者は自分なりに俯瞰(ふかん)した目線での解釈が必要で、ボーッと観ているとシーンに対して表面上の気持ちしかくみ取れなくなり、退屈してしまう。
以上、『沈黙 -サイレンス-』がヒットしなかった理由は、エンタメ要素がゼロで、視聴者が自分で答えを出さきゃいけないからだとご理解いただけただろう。
もともと、10人いたら8〜9人は敬遠してしまう内容の映画なのだ。でも傑作であることに変わりはない。
映画『沈黙 -サイレンス-』のロケ地は台湾!
ちなみに『沈黙 -サイレンス-』のロケ地は台湾・・・。今の日本に当時の長崎の自然を表現できる場所はなかったのかな?そう考えると悲しい。
スコセッシのために、日本の自然をもっと残しておけばよかった。僕は台湾に行ったことがあるが、開発が進んでない自然が素敵な土地がたくさんあった。水が豊富な土地だった。
それはともかく、台湾で撮影したという風景は本当に素晴らしかった。地理的にも日本と近いからか違和感がない。日本だと言われれば、そうなんだと納得してしまう。長崎にしては南国っぽいなあと、ちょっと心の中で思いつつ、17世紀の日本はこんな感じだったのかもと、合理化してしまう。
スコセッシは撮影のために日本の植物を持ち込んだようだし、それだけ徹底した映像を作ったということだろう。
傑作映画を撮っても資金回収ができない!
映画のスクリーンの中で一番苦しんでいたのは、主人公のセバスチャン・ロドリゴ神父 (アンドリュー・ガーフィールド)かもしれないが、公開後に一番苦しんだのは、間違いなくマーティン・スコセッシだろう。
監督自身も手応えがあったであろう、大傑作をやっとの思いで作り上げ、結果は大赤字である。
別に名作が必ず稼げるわけではないので、赤字が絶対ダメだというわけではないが、次回作に資金が集まらなくなるというリスクが生まれてくる。
現に、スコセッシ監督の『アイリッシュマン』には製作資金が集まらず頓挫し、出資したNetflixオリジナルとして公開となった。
2023年の『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』もApple TVオリジナル作品となった(劇場公開も大規模にされたが)。
己の信念を貫き“踏み絵”を踏めないマーティン・スコセッシ。彼は現代で17世紀日本の宣教師たちと同じ苦悩を味わっているのかもしれない。
- ヒューマンドラマ
- ネタバレ, マーティン・スコセッシ監督作品, リーアム・ニーソン 出演作品, 宗教, 感想, 考察
- 1436view